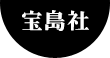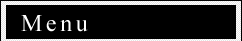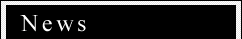第二次選考その他の作品
『BLUE HEAVEN ~空の青、海の蒼~』 安東 たけし
『BLUE HEAVEN ~空の青、海の蒼~』は、大学卒業と就職を経た男女を主人公にした、青春物語です。
「サーフィンの場面は、経験のない人間が読んでも心がはずむ。爽やかな読後感にも好感がもてる」(國岡)、「どこにでもありそうな平凡な設定だが、タツヤとアツシという無二の親友の交流ぶりをうかがわせる描写が物語の各所にあり、香織を挟んで三角関係になってしまった三人の苦しみやとまどいが生々しく伝わってくる」(広坂)など、各場面の映像喚起力と、若者の心情を写し取るその文体は高く評価されました。
が、主要登場人物が途中で事故死してからの展開については、「あまりに安易。一気に引いてしまった」(高嶋)、「一昔前のTVドラマのような展開でがっかり」(梅村)と、評価が一転。最初に登場人物のモノローグで開始された視点が、物語がはじまってすぐに次々と変わっていくところにも問題ありとの指摘がされました。
→ 一覧に戻る
『イン・ザ・ネイム・オブ・ラブ』 福咲 しずく
『イン・ザ・ネイム・オブ・ラブ』は、祖母に死に別れて天涯孤独になった女性が、幼なじみの男性のマンションに居候をし、さまざまな人物との交流を経て癒されていく物語。
「全体に喪失感と優しさが満ちていて、サユミが暮らす湧介の家のゆるゆるで温かい様子が楽しい」(下森)、「世間のルールや常識の尺度に窮屈さを覚えて生きている若者たちに、こんな生き方もあるよ、とそっとささやきかけるような小説。ひとつひとつの言葉がすばらしい」(國岡)と、作品全体の不思議なムードに高い評価が集まりました。
が、ストーリーそのものには多くの注文が飛び交いました。「友達以上恋人未満で、精神的に拘束されることはないけれど、寂しいときには腕枕をして寝てくれる。そんな夢のような男性との関係に説得力を感じさせる意味でも、サユミと湧介の過去のエピソードをもっと書き込んでほしかった」(高嶋)、「ラスト、青年たちがモラトリアムから脱皮していくきっかけが、湧介の姉から無償貸与されていた部屋の賃貸契約が解消されるから、というのはおそまつ。特に主人公のサユミには、自分自身の決意でその部屋から出ていくような展開が望ましかったのでは」(広坂)。
→ 一覧に戻る
『オカンの嫁入り』 めいそう
『オカンの嫁入り』は、結婚して間もなく夫を失い、女手ひとつで娘を育て上げた看護師「オカン」がある日、朝帰りの末につれてきた「捨て男」との人間関係を中心に繰り広げられる悲喜こもごもを、娘の月子の関西弁で語る人情物語。
「話の運びはスローテンポだが、登場人物たちのバックボーンが明らかにされていく中盤からぐいぐいと物語に引き込まれる。とりわけ、お年寄りがイキイキしているのが気持ちいい」(下森)、「何らかの意味で心に傷を負った登場人物たちが傷のなめあいではなく、それぞれの仕方で癒されていく人間ドラマ。説教臭さのほとんど感じられない点が長所だろう」(広坂)と評価された一方で、ほぼすべての選考委員が指摘した難点がありました。
「おトンも早死に、おじいさんも自殺、捨て男が働いていた家のおばあさんも死に、そして最後は主要登場人物も不治の病に。ストーリーをドラマチックにするためかもしれないが、これだけ多くの死が描かれるのは安易」(國岡)という意見にそれは集約されます。また、多くの登場人物が魅力的に描かれている一方、登場場面の少ないオカンのキャラクターが薄いという指摘もありました。
→ 一覧に戻る
『きた娘』 桜庭 豪
『きた娘』は、東京で大学生活の最後の年を過ごしていた詩蔓が、理由も言わずに金沢に就職してしまった一年先輩の庄介を訪ね、狂言回し的なキャラクターの三河の介入を受けながらも、過去の清算(あるいは再生)を試みるという物語。
「大学卒業という人生の岐路に立った今の若者が、考えること、苦しむこと、それらがドラマのように浮かび上がってくる。久しぶりに恋人に会った詩蔓の、庄介の変わったところをするどく数え上げていくところとか、会う前の会話のシミュレーションとか、本気で恋した者ならではの心理描写も見事」(下森)、「もうすでに終わっている恋愛を描いた作品として、着想のおもしろさを買う」(内藤)などの評価が集まりましたが、その一方で「主な登場人物の三人が類型的で、ありがちな自分探しの物語から抜け出られているか、やや疑問」(広坂)との意見もありました。
ヒロインの詩蔓に本音を打ち明けられず、黙って去っていく庄介のキャラクターには、「現代の若者をよく表現している」という意見と、「リアル感以前に魅力がなく、感情移入できない」という意見の両方がありました。
→ 一覧に戻る
『クレイジージェントルマン』 獅子本梓
『クレイジージェントルマン』は、何事にも完璧な人間だが、「実家が寺」というハンデ、「落ち武者がとりついている」というハンデを背負っている鼎が、バイト先にやってくる常連客の「ロイヤルさん」に恋をするというコメディ色の強いラブストーリー。
17歳という作者の若さについては肯定的な意見が多く、「10代の応募者に多いジメジメしていた自己陶酔型の作品ではなく、『人を楽しませる』ということを『言葉の芸』で達成しようという姿勢と、それに成功している力量に感服。作品の途中で妙に主人公に深みを出そうとせず、カラっとした『オバカ』に徹しきっているのもいい。天然系のヒロインの造型も多くの読者に好感をもたれそう」(梅村)と、その文章のセンスは誰もが認めているようでした。
ただ、ストーリーに関しては苦言もあり、「『落ち武者がとりついている』というハンデが、物語の中でハンデとして機能していないのが重大な欠陥。そのため、ロイヤルさんがお客から同僚になった途端、魅力的な女性に見える理由も説明がつかない。ひょっとして、落ち武者が彼のもとを去った時点で、ロイヤルさんへの恋も消えてしまうというようなオチが本来はあったのではないか」(内藤)など、設定の詰めの甘さを指摘する意見も多くありました。
→ 一覧に戻る
『ハッピーエンド』 大川 恵
『ハッピーエンド』は、家庭教師先の母親に恋した大学生や、恋に恋するキャリアウーマン、バツイチ女子大生など、ユニークな登場人物を主人公にした7つの短編集。ささやかな日常のなかでの、さまざまな恋の場面、愛のかたちを切り取る手際が評価された作品です。
「文章のテクニックは高度で、よどみない。意図的に長く文を連ねてうねりや流れをねらった文章も、切れのよいさっぱりした文章もこなす、かなり熟練の筆力」(坂梨)と、その文章力は高く評価されました。
が、エントリーされた作品の中でも唯一の短編集ということで、「7編の物語を『ハッピーエンド』という総題のもとにまとめた意図が見えてこない。それぞれの物語に相互に有機的な連関があって全体を構成するようであれば、高い評価を得られたことだろう」(広坂)という意見が多く、内容を吟味する以前から評価の仕方が問題視される場面もありました。今後もこのような短編集は、選考を通過するのはむずかしいかもしれません。
→ 一覧に戻る
『バニラ&ワイルドダークチェリーパイ』 百成 ヒロオ
『バニラ&ワイルドダークチェリーパイ』は、高校2年生のヒロイン斗和子と、家の離れに閉じ込められていた十三歳の少年、笙太との不思議な交流と別れを描いた不思議な物語。
「主人公の少女が、13歳の少年の姿をした死霊に処女を捧げるという背徳的なエピソードが物語の中心に据えられているが、陰惨さはなくエロティックでありながらどこか清々しい印象すら感じられる。作者ののびやかな文体や、斗和子の告白の聞き手・銀ちゃんが闊達な性格の青年として設定されているもさることながら、斗和子が死霊・笙太の妄執を晴らして成仏させる物語でもあるからだろう」(広坂)と、その着想の面白さに高い評価が集まりました。
が、「文章はすっきり的確で、洗練されているが、笙太を『初めての男』に選んだ斗和子の心理がつかめないせいか、そのことを今のボーイフレンドに告白しようと決めた切実さが伝わらず、読後感がもやもやしてしまった」(坂梨)という指摘もありました。
笙太が亡霊になるバックボーンを描いた明治時代のエピソードと、現代の女子高生の斗和子のエピソードとの融合についても、「うまくいっている」という意見と、「ちぐはぐな印象を受けた」という意見の両方がありました。
→ 一覧に戻る
『ひよこのリリィ Lily The Chick』 山ノ内 結
『ひよこのリリィ Lily TheChick』は、京都祇園生まれの才媛、井田千由里が、実の父ではないかと疑う大学教授の藤崎と、アメリカ人青年ジュリアンとの間で恋に揺れるという物語。京都の芸妓の世界や茶道の精神についての考察からはじまって、上田秋成論、源氏物語、忠臣蔵、バリ島のヒンドゥー教などを教養をふんだんに取り入れた才気あふれる力作です。
「教養があり、才能があり、かつ、そのことを明確に自覚している『可愛くない女』というヒロインの造型に独創性を感じた。また、そんな彼女が実は、強い力で自らを保護してくれる存在を希求し、そんな自分に時に苛立ち、その苛立ちの呪縛を自ら断ち切ろうとしている姿に共感を覚えた」(梅村)という評価の一方、「文学的な知識が盛り込まれた文章は、多少ペダンティックに過ぎるようにも思う。読者を放っておいて、著者の筆だけが走っていく、自己陶酔の匂いが鼻につくのが難点」(梅村)と、同じ選考委員が語るように、長所短所の両面を同時に指摘する選考委員が多かったのも事実です。
「作中に挿入される上田秋成論(「菊花の約」論)がもっと物語の展開に大きく関わるようなものだと面白かったと思うのだが、結果としては秋成よりも、やはり作品中に言及のある『源氏物語』の方が、ヒロインの運命を暗示している。日本文学の学生が主人公なので、文学の話題がちりばめられているのはある意味で当然だが、物語との関連が薄いと衒学趣味と受け取られかねない」(広坂)との指摘もありました。
→ 一覧に戻る
『ファッキン・エンジェル』 プレイディーみかこ
『ファッキン・エンジェル』は、語学留学生の「わたし」が、美貌の詩人ジョンと燃えるような恋物語を繰り広げる勢いのあるラブストーリーです。
「自伝的要素の大きい作品は、リアリティをもつ反面、ともすれば自己中心性が強くて辟易することがある。これは、ばからしいほどの駄目男への溺れっぷりを、ユーモアと悲壮と情熱でもって喜劇にしている。みごとに客観化しており、エンターメントとして楽しめる。ドライで切れ味鋭い文章。独特の擬態語、修飾語が効果的」(坂梨)といった高評価が集まりましたが、反対に「でれでれでグニュグニュの男女関係の不思議さ、深み、泥沼、喜び、悲しみを思う存分に描いていて面白かったが、二人の関係のあまりのしつこさにうんざりする部分もあった」(國岡)という意見もありました。
「残念ながら、登場人物たちの心の中に棲みついている破滅願望や切なさがいまひとつ伝わってこなかった。それはおそらく、著者の主人公たちに対する甘さの表れだと思う。徹底的にクールな不良小説にしたほうが、かえって読む者にインパクトを与えられたのではないか」(梅村)、「自伝的なものではなく、ストーリーに比重を置いた作品も読んでみたい」(高嶋)との意見も多く出ました。
→ 一覧に戻る
『ママの恋人』 秋元 史江
『ママの恋人』は、高校生のヒロイン千秋が、母親の麻樹と同じ男性と恋をしてしまうというユニークな物語です。途中までふたりの恋の相手が同一人物だと分からず、それがいつ明かされるのかといったサスペンスで読む者をぐいぐいと引きつける部分が印象的な作品でした。
「成長する娘を見て、自分が『おばさんになる』ことへの焦りといらだちを感じる母親の心理描写にうならされた。いくつになっても女として見られ、女として人生を楽しんでもいい時代、多くの女性の共感を呼ぶのではないか」(高嶋)と、登場人物に素直に感情移入した委員がいた一方、「母の心象風景にリアリティはあるが、娘の恋愛は、母の恋愛を引き立てるための甘い飾りになっているような感を受ける」(梅村)との評価もあり、意見は分かれました。
「千秋のボーイフレンドの橘が、『好きではない麻樹さん』と肉体関係をもったことの理由や心情が語られることなく、キャラクターが矛盾している」との指摘もありました。
→ 一覧に戻る
『ミスプーケット』 東恩納 真珠
『ミスプーケット』は、タイのプーケットに移住し、バーで働きながらなんでも屋を営んでいる美樹が、ゲイの健一の恋人探しに奔走するという物語。
「ハワイともバリ島ともちがう、タイのプーケットならではの生活、風景、楽しみを細かいところまで具体的に描いていて、興味深く読み進める。美樹や匠など登場人物の魅力も上手く引き出し描いている」(下森)など、舞台設定と情景描写、人物造形におおむね高い評価が集まりましたが、メインプロットである「健一の恋人探し」については、「最後に健一と付き合いたいという男性が現れただけで、みんなして万歳では、楽天的に過ぎる。消化がよすぎて、インパクトに欠ける」(坂梨)との意見が多く出ました。
また、「プーケットの自然や風俗などはよく描けている一方、「オカマ」と書かれた人たちに対する作者の蔑視にも似た視点が気になる。そちらのほうももっとよく取材して書き込めば、もっと厚みのある小説になったと思う」(内藤)との意見も何人かの選考委員から指摘されました。
→ 一覧に戻る
『ラピスラズリの囁き』 中森 泉
『ラピスラズリの囁き』は、大学卒業を目前に控えた麻由が、かつてフランスのパリで画家修業をしていたという父親の祐志の足跡をたどるという物語。麻由のストーリーの合間に、若き父親のパリ時代のエピソードが差し挟まれるという構成の妙も、この作品の魅力となっています。
「深い青色で染め上げたような作品で、過去と現在を織物のように交互に繰り返していく手法も成功している。小説としての面白さと読後感の爽やかさを評価したい」(國岡)という意見や、パリ生活にくわしい選考委員からも現代のパリについての描写の確かさについて好評でした。
ただ、「舞台が父親の若かりしころである、1970年ごろのパリになった途端、急にリアリティが感じられなくなったのが残念」(高嶋)という意見については、多くの委員が同意しました。70年代パリといえば、5月革命などでフランスが熱く燃えた思想と政治の時代。田園が舞台といえども、日本から留学してきた画学生がこうした運動にまったくコミットしていないというのはいささか不自然かもしれません。
→ 一覧に戻る
『愛なんて飼い殺せ』 九神 玲
『愛なんて飼い殺せ』は、父親が初体験だったという愛美が、恋人の友達との二股や援助交際などの奔放な生活を描くかたわら、遠縁のホスト、ガクや友人たちとの交流と死別などを経験して成長していく物語。
「『カモン ベイベー』『にゃうん』といった、一見意味もないような言い回しは可愛く温かく、読み手を不思議と和ませ、明るくさせてくれる。この作品の魅力の一番だ」(下森)、「若い女性の口語体で書かれているが、文章はしっかりしており、比喩や慣用句なども適切。文章力のある筆者が表現のスタイルとして口語調を選んだもので、素朴な自分語りとは一線を画している」(広坂)と、その文章力は高い評価を受けました。
が、「無駄に長い」との意見も多く、「これでもかというほど不幸続きの前半に比べて、癒しと自立の後半がやや冗長。ガクの事故死後のエピソードを整理して、焦点を絞った方がよかったのでは」(広坂)といった意見には、多くの選考委員が同意していました。
『一角獣の夏』 桐島 留衣子
『一角獣の夏』は、画廊に勤める理央が、高級レストランを経営する大会社の御曹子、界と出会い、妻との死別による深いトラウマを癒そうとする物語。悲劇的な結末も意表をついて、ドラマチックなストーリー構成が印象的な作品です。
「普通の女の子が、大会社の御曹司に一目惚れされる。若い頃に一度は見る夢のような話に引っ張られ、すぐに物語の世界に入れた。また、その御曹司の接近に別の目的がありそうな気配が牽引となり、クライマックスまで物語を力強く引っ張っていく」(下森)、「建物や部屋の内装などの描写はうまい」(坂梨)と、導入から前半までのストーリーには誰もがすんなり感情移入できたようでしたが、後半になって興を削がれてしまった委員も多かったようです。
「界がトラウマを克服するためにたくらんだ計画というものが不明瞭で、死へ至る登場人物たちの心情に共感できない」(坂梨)という意見や、主人公の視点で始められた物語が途中でどんどん他の登場人物に移ってしまう文章もマイナスの評価を呼びました。
→ 一覧に戻る
『十四人目の男と私』 粒山 吉樹
『十四人目の男と私』は、38歳のOL由加が、「明日、14人目に出会う男性が運命の人です」という夢のお告げによって、チビ、ヤセ、毛深いという、生理的に受け付けなかったはずの洋介との恋を成就させるまでの物語。
「全然タイプじゃない容姿の男ヨウスケに一目惚れされた由加が、戸惑いながらもやがて彼の気持ちを嬉しいと思い始める。そのプロセスが自然でリアルに描かれている。おかげでファンタジーにならず、実際、そういうことってあるかもと思わせてくれた。タイトルも、いい」(下森)といった評価の一方、「『女は生理的に受け付けない男をどう愛するか』という興味深いテーマを扱い、最後に主人公の成長を描いてハッピーエンドにしていながら、どこか読後感が悪い。その理由は、『男は顔じゃない』というメッセージよりも、『トウのたった女性は、相手の容姿にこだわるべきではない』というメッセージを強く感じてしまったからか」(高嶋)といった不評も多くありました。
→ 一覧に戻る
『永遠の薔薇の祈り ピエール・アベラールとエロイーズの恋の物語』 岡田 康枝
『永遠の薔薇の祈り ピエール・アベラールとエロイーズの恋の物語』は、アベラールとエロイーズの書簡集をもとにした創作小説。性に無知だったエロイーズが、哲学者のアベラールによって成熟した女性に成長していく様や、スキャンダルによって離ればなれになっていく悲劇の運命が丁寧な筆致で描かれます。
「原典の『アベラールとエロイーズ 愛と修道の手紙』(岩波文庫)と比較して読んだが、このような物語を編み出した著者の力量に驚きを感じた。中世に生きた人々の息づかいが聞こえてくるような、現代的なリアリティ。恋愛小説としてもすばらしいが、それを超えた全体小説として、読むものに小説の醍醐味を感じさせてくれる」(國岡)、「かの難解な〈普遍論争〉を爆笑問答として描き出すなどの茶目っ気もあって、現代人が読んで楽しめるロマンとなっている」(広坂)などの高い評価が集まりました。
ただ、その一方で聖書に関する記述の甘さが指摘された他、「珍しい時代背景と特殊な状況の話には新奇なことが多く興味深いが、登場人物に魅力を感じないのが難点。若いころ、それぞれ傲慢で自分勝手、おろかで頑固だったアベラールとエロイーズが後半、聖職者として再会する場面では、人柄や言動があまりにもかけ離れていて、受容しがたい」(坂梨)、「これほどの構成力、文章力があるならば、ぜひともオリジナルな物語で勝負して欲しい」(下森)という意見もありました。
→ 一覧に戻る
『鏡寧寺モラトリアム』 家愁夏
『鏡寧寺モラトリアム』は、地方の大学に入学した前田潤一が、ひょんなきっかけから古風な男言葉をしゃべる7回生の「師範」と同居し、弟子を名乗る同居人らとさまざま不思議な体験をするというファンタジー作品です。
「不思議な主人公に不思議な空間と時間。それを文章力でリアリティあるものにし、上手く物語にのせている」(下森)「夢と現実の境界線上にあるような不思議なムードを持つ作品。登場人物の擬古文調の言い回しに若干のミスが散見されるが、読みづらさはない。理屈をこねるより、作者の想像力がつくりだした世界にドップリ浸っていたいと思わせるだけの力がある」(広坂)など、作品全体を貫くムードは大いに評価されました。
その一方、「すじがきの考慮がいまひとつで、いきあたりばったりという感じがする。春の朧夜のような独特の雰囲気が行間に満ちて、道具立てなどもおもしろいので、ストーリーをもっと練り上げてほしかった」(坂梨)、「肝心の師範のカリスマ性を示す具体的なエピソードが足りないのが惜しい。なぜ弟子たちが師範にあこがれるのか。単なる変わり者ではない師範の魅力を初期段階でしっかり描いて欲しかった」(高嶋)といった意見もありました。
とはいえ、「20歳という若さで、これだけの独自の世界観を描ける作者の才能は高く評価したい」(高嶋)というのは選考委員ほとんどの意見でした。
→ 一覧に戻る
『山疼き』 佐藤 竜一郎
『山疼き』は、新聞記者の沢本が、同期入社の一風変わった男、桜川が失踪した真相を探るうち、美術界のひとくせもふたくせもある人物らと出会い、耽美的で露悪的な世界に出合うサスペンス色の強い作品です。
「文章は緊密で、情景を描出するうまさがある。読み手の心をざわざわと波立たせるような不穏さと、曲者ぞろいの登場人物によってミステリー色を強め、展開に期待をもたせる」(坂梨)と、文章力の確かさには誰もが感心したようですが、最後に明かされる謎解きの部分は、「女性ふたりの手紙や告白にのみ頼っており、主人公が真相に迫る様が描かれていないのは難点」(梅村)と、多くの委員が指摘していました。
また、「登場人物の会話に説明的なぎこちなさを感じる。警察署長、山の案内人など人物像がステレオタイプなのも気になる」(広坂)、「真相は、ミステリーとしてはお粗末。『世をすねて、親ともども無理心中しようとしました』というのではガッカリ。ミステリー仕立てにするのではなく、最初からその真相をバラしておいて、桜川の耽美主義から発した異常性、幼児性、エゴイズムにスポットをあててじっくり描くべきだった」(内藤)などの意見がありました。
→ 一覧に戻る
『紫色のスープ』 石井 恵太朗
『紫色のスープ』は、介護問題に真正面から挑んだ意欲作。画家を目指す恭吉と、みつという女性との間に立ちふさがる寝たきり老人との同居生活は凄絶で、ホラー作品かと思わせるような迫力がありました。
恋などの字を旧字にしたり、冒頭の擬古文体が「気取り過ぎ」との評価があったものの、冒頭以降の文章には「日増しに壮絶になっていく介護の様子から、部屋に漂う緊張感と徒労感がひしひしと伝わってくる。極限の緊張と疲労の中、それゆえに2人の思いと欲望が募る様も、熱となって浮かび上がる」(下森)との好評が集まりました。「幻想小説ふうの味わいの中に、リアルな介護の苦悩がはいってきたり、乱歩ふうのグロがあったり、奇妙な密閉空間にとらわれた気分になる。欠点も魅力も独特なものがある」(坂梨)、「恭吉がみつの家に住むことを決心した途端、帰る家がなくなってしまうところ、そして終盤の濡れ場、紫色のスープを飲もうとするところなど、ハッとする名場面がある」(内藤)といった評価が上がったあたりはオリジナリティも十分といった感じ。
ただ、「ヒロイン・みつが、どうも男性(特に中年以上の男性)から見た『理想像』の域を出ていないのではないかと思える」(梅村)、「設定は面白いのだが、登場人物のことごとくに共感できず、うまく感情移入できなかった」(高嶋)といった評価もありました。
→ 一覧に戻る
『雪の晶 ―二つの恋の鎮魂から―』 島本 青玄
『雪の晶 ―二つの恋の鎮魂から―』は、若いころ大地主の娘ノブと駆け落ちして雪深い山奥で炭焼きをしている老人熊吉が、彼と同じ駆け落ちによって追っ手から逃げのびてきた学生をかくまう悲恋の物語。
「男として枯れきれないまま、孤独な運命を淡々と受け入れて残りの生を紡ぐ主人公熊吉の描き方は、切実さがあり、なかなか読ませる」(梅村)、「前半、熊吉老人の視点から描いた章は、深い孤独と哀感が漂って、風景の色彩がくっきりと浮かび上がってくる詩情があり、印象深い」(坂梨)と、前半の文章の高い描写力には高い評価が集まりました。
ただ、「中盤の若い2人の逃避行の部分は、芥川龍之介なども登場してそれなりに見せ場があるのだが、冒頭と結末の熊吉の物語の間に入った添え物のような印象を受けてしまい、作品のパワーを相殺してしまっている」(内藤)という意見も多く出ました。
→ 一覧に戻る
『太陽と向日葵』 あんな
『太陽と向日葵』は、19歳の作者の手による青春小説。不特定多数の男性たちと「セフレ」の関係を続ける高校1年生の葵が、太陽みたいな笑顔をたたえた先輩の陽と出会い、自分を取り戻していく物語です。
「読んでいくうちに、高校時代の恋を思い出した。苦しくて辛いことがいっぱいなのに、思い出せばなぜかすべてキラキラしている、あの時代のあの思い。この作品には、そのキラキラの要素が小さなものも大きなものも、もれなく描かれている」(下森)と、誰もがそのみずみずしい文章に惹かれた様子でした。
が、「ラストが説教くさいのが気になる。それまでのストーリーで、作者のメッセージは十二分に表現されているので、作品の完成度を考慮するなら、亡くなった恋人の手紙だけで充分なエピローグになったように思う」(広坂)、「ヒロインがなぜセックス依存症になったのか、その心の闇が見えてこなかっただけに、不完全燃焼のような印象を受けた」(高嶋)といった意見もありました。
→ 一覧に戻る
『東京プリン』 三村 真喜子
『東京プリン』は、地方の会社に入社して3年目のOLみちるが、幼なじみのサキちゃんの誘いを受けて東京でプリン専門店を開店する顛末をほのぼのしたタッチで描く好編です。
「プリンという小さなお菓子を中心にすえて、これだけの物語を書ける文章力を評価したい。派手さも奇抜なストーリーもないが、温かさがあり、安心してゆったりと物語の世界に入りこんで存分に楽しむことができる。登場する一人ひとりのキャラクターがイキイキしていて、読者の心を温かくする物語には捨てがたい魅力がある」(國岡)と、ヒロインのプリン作りにかける奮闘に多くの委員が感情移入したようです。
しかし、つきあって7年の恋人の優一とのエピソードは、「一本調子」との評価が多く、「浮気現場を見てしまい、失恋しておしまい、というのはなんとも寂しい。なんかもう一ひねり、主人公に人間くさいところ(もしくは修羅場)が欲しかった」(高嶋)という意見が大勢を占めました。
→ 一覧に戻る
『里中禅右衛門と倫』 錦糸帖 始
『里中禅右衛門と倫』は、4歳から44歳まで、家族以外誰にも会うことなく幽閉されていた禅右衛門の娘、倫の凄絶な恋情を描いた歴史物語です。
「倫が文通する間に募った泰山に対する激しい思い、ついに泰山に会ったときの違和感、助手の弾七に対する気持ちの揺れ。これら、世間を知らずに育って成人した女が初めて感じる男に対する感情が、非常に生々しく描かれている」(下森)、「少女、青春時代を幽閉という形で凍結されていたゆえの傲慢や渇き、そして、何より、自らの『若さ』を『不潔』だと感じる彼女の感性にドキリとさせられました」(梅村)などの評価が集まりました。
ただ、同じ題材を扱った小説に大原富枝の『婉という女』という作品があり、「野中兼山と一族の悲劇を知っている人にとって、前半は梗概を読んでいるような味気なさを感じる。過去の名作に挑むなら、高いハードルを越えるつもりで臨まねばならない」(坂梨)との意見もありました。
→ 一覧に戻る
『恋路線』 村岡 直樹
『恋路線』は、なぜか出会う人出会う人に頼まれごとをされてしまうバスの運転手の市原雄介が、自分の恋をそっちのけで奮闘する人情喜劇。
「実直さだけが取り柄の、やや引っ込み思案な主人公の周囲で、次から次へと事件が起こるのは、考えてみればまずありえない話で、小説ならではのウソなのだが、それに違和感を覚えさせないのは作者の手腕だろう。主人公の生業であるバス運転手の日常、彼が想いを寄せるデザイナーの仕事場などがていねいに描写されており、読み進めるうちに、主人公の暮らす町を知っているような気分にさせられる」(広坂)と、素直に作品の世界観に浸った選考委員が多かったようです。
ただ、「事件やエピソードを盛り込みすぎて、あわただしい」(坂梨)との意見も多く、さまざまな矛盾点が指摘されました。念のため、そうした意見を下に添えておきます。
「バスジャック犯が捕まったあと、市原をはじめ乗客らが取り調べもなしに放免されてしまうのはおかしい」、「実家が火事で焼けてしまった同級生を助けるために援助交際をしてお金を稼ごうとする女子高生の発想はいくらなんでも短絡的」、「しかもそのことを市原に指摘されたときの女子高生は、突然、はすっぱな不良少女になっていて、前の登場シーンとギャップがありすぎる」「その女子高生のことを相談してくる友達の行動が不可解(市原に相談を持ちかけておいていっさい協力しようとしないところなど)」「バスの中で市原をにらみつけたチンピラを放火犯だと推理した、市原の根拠が薄弱」「白井は何の根拠があって探偵でもない市原にダイヤ探しを依頼したのか」「真一郎老人は、なぜ都合良く市原に自分がダイヤの窃盗犯だと告白したのか。あまりに都合が良すぎる展開ではないか」「冒頭では包容力があって、尊敬していた白井先輩は、なぜ最後になって仕事人間になってしまったのか」
→ 一覧に戻る
『禧い棲むと人の言う』 清水 みのり
『禧い棲むと人の言う』は、離島の医師をつとめる「子門」と、失恋に心を痛めるOLの蓮子の淡い恋を描いた作品。医師と蓮子を交互に主人公にした連作短編の形式をとっており、各編に謎解きの要素が仕掛けられていて、最後まで安定感のある作品として評価されました。
「しかも、各章に必ず宝石が関係しているという構成も凝っていて、評価に値する。話の展開と盛り上げるタイミングも抜群にうまい」(下森)。
ただ、その一方で「軽く読める連作短編だが、薄味。少なくともラブストーリー大賞をねらうような意欲作にはみえない」(國岡)、「どの登場人物のキャラクターもきちんと立っているし、好感の持てる人達なのだが、『これが清水みのりの作品だ』と訴えかけてくるような著者の個性を感じない」(下森)、「『離島の医者もの』というと、ドラマにもなった大ヒットマンガを思い出してしまう。同じ『離島の医者』を扱うにしても、もう少しひねったキャラクターを創出してほしかった」(高嶋)といった意見も多くありました。
→ 一覧に戻る