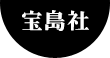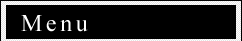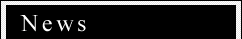最終審査講評
浅倉 卓弥 Asakura Takuya / 作家
『守護天使』上村 佑
現在幾つの公募新人賞があるのか正確にはつかんでいないが、この作品に大賞を授賞できるのはおそらく本賞くらいではないかと思う。どこがラブストーリーだといわれれば言葉につまるし、何よりタイトルだって詐欺スレスレである。本作にはガブリエルもミカエルも出て来ないし繁華街の自警団も登場しない。それどころかこの天使はふんどしの上に三段腹を載せている。
選考を終えてみるとこの作品だけが初めから別の土俵に立っていたような気もする。実際ディテイルとか説得力とかいった観点でみれば突っ込みどころは満載なのである。ところがとにかく読ませるのだ。気がつけば、いや、それはちょっといくらなんでもやりすぎだろうと、選考を忘れて含み笑いしながら読んでいた。読み進めるうち、ひょっとするとこちらに突っ込ませるのも作者の芸風なのではないかという気さえしてきた。柴犬のトイレのくだりでは素で笑ってしまったことを告白しておく。
実際冒頭から主人公はとんでもない理由で会社を解雇されている。普通は有り得ない。不当解雇という言葉さえもったいないくらいの馬鹿馬鹿しさである。この作品世界をこういうものだと受け入れられるかどうかで本作への評価は大きく変わってくるだろう。
とはいえ、核となる事件の決して単純ではない内容をこれだけタイトな枚数で明らかにする手つきは確かなものだし、何よりもサクサクと読めてしまう文章のスピード感が他の候補作から頭二つ分くらい抜けていた。
もう一つ大賞受賞の決め手となったのは、特に書店員の方々による三次選考において本作への評価が極めて高かった点である。さて刊行後この作品がどのような読み手にアピールするのか。来年の応募傾向にはどう影響するか。また大賞作品は映画化が決まっているのだが、はたしてどなたがこの主役に名指しされてしまうのだろうか。などなど、関係者の一人として僕も今から楽しみが尽きない。それもまた作品の大きな魅力の一つであることは間違いないだろう。
『一秒でも長く君と同じ世界にいたい』 かわなべ かろ
作者の才気という観点から一番可能性を感じたのは本稿だった。最初は文章のあまりの雑さに閉口したのだが、読み進めるうちほとんど気にならなくなりさえした。
まずトピックの出し入れと、伏線の導入と回収にかかる手つきが素晴らしかった。本作は不条理な現在と日常的な過去を交互に配置していくというクロス・カッティングの手法で書かれているのだが、この切り替えと連結が非常に巧妙だった。両方のパートでそれぞれに語られるトピックが微妙にエコーして物語が進んでいくのである。また、過去パートに限ってもかなり時系列をいじって展開されているのだが、こちらも混乱なく読めるように構成されている。こういうセンスは望んで身につけようとしてもなかなか持てるものではないと思う。
イメージの独創性にもかなりプラスの評価をした。砂漠に忽然と立つ電話ボックスと四方を海に囲まれたボートというのはありそうでなかなかない設定だと思う。最後の場面で砂の中から立ちあがるヒロインには美しさを感じもした。
大賞は無理としても何らかの賞をという気持ちもなくはなかったのだが、本作には文章以外の部分にも内在する傷が少なくなく、しかもそのそれぞれが大き過ぎた。主人公と両親の事故、それから襲撃者とを結ぶ要素としてある企画書が登場するのだが、この内容が最後まで明かされない。思いつけなかったのかそれとも最初から考えもしなかったのかはわからないが、このトピックでかなり引っ張っているのだから書かないのはやはり不親切を通り越して失礼だろう。ただ殺人者という言葉を使いたかっただけだったのかと勘繰られてもしようがない。
また、主人公の行動や思考のロジックに首を捻らざるを得ないところがあまりにも目についた。現実に即した過去パートでも、上司を殴りに向かうくだりはもう少し説得力のある心理描写が必要だろう。現在パートの主人公の思考パターンはあえて捻ってあるのだとは想像するのだが、だとしてもこれは、最後に明かされるこの語り手の存在の特異性と何らかの形でリンクさせ、ある種の論理のもとに統御されていたことが読み手にきちんと明示されなければならない種類の内容である。これらの欠点はとても一朝一夕には修正可能なものではなく、今回の賞での刊行は無理だと判断せざるを得なかった。
いずれにせよ、冒頭から十行も進まないうちに「目覚まし時計」が四回も出て来るような無神経な文章では普通なら最終候補にまで残ることはほとんどないはずである。にもかかわらず本作がここまで上がってきたのは、各段階の選考委員が僕と同じようにこの作者の可能性を強く感じたからだと思う。是非まずは文章力を磨いていただき、いつかまた別の機会に新たな作品を読ませていただくことが叶えばと願っている。
『カルナ』 長月 雨音
筆力は圧倒的に高かった。もちろん一人称は基本的に破綻しにくいという利点もあるにはあったのだけれど、前回の候補作までを含めてもトップクラスだったといえる。
一応難点を挙げておくと、意図的に冒頭とクライマックス直後に使用したと思われるオノマトペがむしろ逆効果にしかならなかったところと、現在形の文末の使用にところどころ違和感があったこと、それから、テトラポッドの積み上がった様などやや複雑な地形や意匠を描写する際に、筆が走り過ぎてかえってイメージが不鮮明になってしまっている部分が目についた。
着想も優れていたと思う。『カルナ』というあまり一般には馴染みのない言葉を見つけてきて、これを悲しみに伴なわれる一つの感情として定義しなおし、そのうえ形や人格さえ与えてみようという試みは、ある意味では小説ならではのものだなと感心しもした。
以上のようなアドヴァンテージにもかかわらず本作をまったく推すことができなかったのはひとえに主人公の設定の致命的なまずさによる。
脳生理学にかかる記述を違和感なく地の文に取り込むために語り手を医学生にせざるを得なかったのだろうと推察はするのだが、これが結果的に読み手の共感を大きく阻んでしまう要素として立ちはだかってしまった。そのうえ本来彼の傷として機能しなければならない失恋がほとんど書かれていないものだから、自殺の決意もただの自己憐憫としか取れなかった。
ちょっときつい表現になるが、母子家庭とはいえ援助してくれる人間がいて医学部まで行かせてもらい、バイトの金は彼女との海外旅行につぎ込んで、自殺するんだといいながらも試験はそつなくこなし一方で部活の人間には迷惑ばかりをかけている。ここに書かれた主人公は視点を変えて記述するとこういう人物にるのである。ほかの要素にも読み手の共感を誘う素地がほとんどなかった。
どれほど文章を精査しどれほど緻密なクライマックスを準備しても、これではすべてが生きて来ない。作者には、各段階の選考を通じて主人公に甘えを感じたという評価が重なったことを十分に吟味してほしい。
もう一つ注文をつけると、これほどの筆力の持ち主であればこそ、クライマックスの光景は外国の固有名詞に頼らずに描写して欲しかった。中国やヨーロッパを出さずに高知の話に留めて我慢するだけで全体の印象もずいぶん違ったものになっただろうと想像するからである。それと、全体にもう少し絞れるとは思うのだが、特にこの場面は冗長に過ぎて感じられた。いずれにせよ、捲土重来を期待する。
『夏の雪兎』 高田 在子
文章の安定感は『カルナ』に次いでいた。主人公の設定も多くの読み手に支持される可能性を感じさせるもので、実際百枚目辺りまでは今年の大賞はこれで決まりかなと思って読み進めていた。居酒屋で啖呵を切るくだりでは主人公に喝采を送りもした。
ところが後半に入って評価は一転してしまう。相手役である幸人の視点の無造作な導入がすべてを壊してしまったのである。果たして作者はどちらを書きたかったのだろう。主人公の成長か、それとも二人のハッピー・エンドの方なのか。
前半はヒロインの成長物語として極めてよくできている。たとえば結末が同じだとしても、この作品は我慢して最後まで千可子の視点で書かれるべきだった。幸人の過去を幸人の視点で書くのは簡単である。ところがそうなると読み手には、どこまでが千可子もわかっている内容なのかという点が判断できなくなる。前半をかけてせっかく縮めてきた読み手とヒロインとの距離が一気に開いてしまうのである。書く側が楽をしてしまえば読み手に伝わるものは自ずと少なくなって当然だろう。
特に本作のように作中の事件が出会いとか退職といった日常レベルの内容に留まる場合には、どうしてもプロットの起伏は小さくなり、必然的に心理描写が作品の鍵となってくる。ところが作中に複数の視点を導入してしまうと、それぞれの登場人物への読み手の感情移入は全体に浅くならざるを得ない。この作品の場合、前半はほぼヒロインの視点で話が進むのだが、後半に入っていきなり相手の視点と交互に展開されるかたちになる。明らかにその方が書き易いからだ。この安易さが、ヒロインの退社後に開示されるエピソードのすべてを取ってつけたような印象にしてしまった。根本的な構成ミスだろう。どうしても複数の視点で物語を書きたいのであれば、最初からある程度のバランスをとって両方の視点を導入しておかなければならない。
この理由から、ヒロインが何故過去の恋人の死を乗り越えることができるのかという肝心な部分でさえ、一応庭仕事と絡めて書こうとはしているのだが、読む側にはまったく伝わって来ない結果となってしまっている。もう一方の幸人のパートに関してはほとんどリアリティーを感じなかった。ついでながら、終わり間際でいきなり紹介されるメグという学生の主人公との関係の設定には破綻が残っているように思えた。また、この視点の切り替えに作者自身も混乱したのか、千可子の視点でしか語り得ない情景描写で幸人のセクションが始まっている箇所もあったことを指摘しておく。
念のために付記しておくが、複数視点の作品がすべてだめだといっている訳では決してない。事実今回の大賞作品はこの手法を採用し成功している。視点の問題は物語が描き出そうとしている内容と密接にリンクしているのである。
やや説明過多な癖はあるが地力はできている。何を一番読み手にアピールしたいのかを御自身の中で明確にして、その着想が十分生きるように考えながら次作に挑んでいただければと思う。
『style』 広木 赤
男女の視点人物を設定し、クロスカッティングの手法を用いて、始まる前に終わってしまう一つの恋愛を描き出そうという着想を高く評価した。だがいかんせん長過ぎる。脇役の自殺というイベントこそあるけれど、基本的には何も起きない二人を書こうとしている訳だから、せいぜい二百五十枚が限度であろう。それが四百枚も延々と続くものだから、作者には申し訳ないが途中でうんざりしてしまった。
まず何より文章に不要な要素が多かった。作者の年齢を鑑みれば各文は破綻もなくきっちり書けてはいるのだが、随所に無駄なものが残ったままなのである。少し長いパラグラフになると必ず一つか二つはそこに置かれる必然性のない文が見受けられた。二度三度なら許容範囲だが、ほとんど毎回では読む方はやはりたまらないのである。エピソードも同じである。全体のバランスを見ずに書きあがったままをそのまま応募したという感が否めなかった。誤字脱字のチェックだけが推敲ではない。削る箇所はきちんと削る習慣をつけていただきたいと思う。
また、作者は同じ構文を語句を入れ替えてたたみかける手法を好んで使っているが、これも頻度が高過ぎる。前半で何度も同じパターンを見せられているので、ヒロインが我知らず手首を齧っている場面や、あるいは主人公が指を持ち帰る箇所など、キメなければならない肝心なところでこの手法が出て来ても、またかという感想がまず先に立ちすっかり効果を削いでしまっていた。
ただし描写力には目を見張るものがあった。上で言及したヒロインがリストバンドを外す場面もそうだが、無人の公園で血を流しながら踊る彼女や、彼女と自殺する少女のデパートでのやりとりなど、独特な印象を鮮烈に残す場面が作中には多々あった。
特にヒロインを描いた部分には奇妙なほどのリアリティーがあり、僕だけでなく各選考委員が非常に感心していたことを報告しておく。逆に作者自身の立場と重なる主人公の描写の方が地に足がついていない感じがするのは、まだ学生という存在を客観的に見られていないせいかもしれないが、これは現実的に仕方のないことだろう。むしろ想像で書いた箇所の方がリアルだというのは作家的なセンスがあるということだともいえるのではないかと思う。あるいは女性パートだけの物語だったらもっと強く推していたかもしれない。
もう一つ、この構成を選んだことは作品に相応しかったとは思うのだが、前半はともかく二つの物語を交錯させてしまってからは目を覆いたくなるほど語り口が不安定になってしまっていることを指摘しておく。時間が行きつ戻りつし、肝心な箇所が書かれていなかったりした。形式は遵守したままでかまわないが、トピックを注意深く選んでもう少し読み手にわかりやすく構成していくべきだったろう。結局最後まで、物語の世界に引き込まれるのではなくつきあって読んでいるという感が拭えないまま終わってしまった。
資質を買うからこそ、むしろ作者にはまず現在の学校をきちんと卒業して保護者への借りを返し、二三年実社会の水を飲んで来てからまた小説に挑んでいただきたいと思う。取材のつもりで就職するのでもかまわない。もちろん時間を作るのは大変になるが、衣食住を独力で維持する経験は必ず視野を広げてくれるはずだし、いずれ作品の内外で自身を助けてくれるだろう。これは一応僕なりのエールなのだが、どう受け取っていただけるかは結局作者に委ねるしかない。