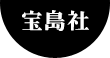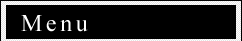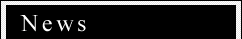最終審査講評
剱持 嘉一・渡辺 真貴子 Kenmotsu Yoshikazu・Watanabe Makiko / エイベックス・エンタテインメント 映像企画部 部長代理・映像企画部 企画開発ルーム
『守護天使』 上村 佑
『守護天使』 上村 佑
「話の転がし」が非常に上手く、上記で挙げた観点からすると、最も映画的な作品でした。冴えない中年男が女子高生をただ、人知れず見守ることで愛情を表現する……。見返りを求めることの無い、「無償の愛」がいいですね。最終選考会でも出た例えですが、ヴェンダースの『ベルリン・天使の詩』ユーモア版、といったところでしょうか。「ラブストーリーは必ずしも、恋愛が成就する話ではない!」という当たり前のことに気付かされました。主人公の日常のバカバカしさと悲哀が笑える一方、憧れの女子高生の作成した厭世的なブログが導いていくサスペンスの世界が物語に幅を出しています。少々、突っ込みたい点があったり、もう少し主人公が最終的に別の形でも報われてもいいような気もする等、細かいところを挙げれば多少ありますが、それよりもまず、勢いとエンタメ性、そして巧妙なリードに引き込まれていきました。意外なところで、「鬼嫁」のキャラクターが良く、ユーモア小説はホロリで締まる、という「鉄板」もバッチリです。まさに、「変化球」からのラブストーリー大賞作品で、個人的にも嬉しく思っています。
『一秒でも長く君と同じ世界にいたい』 かわなべ かろ
粗削りながら何か引っ掛かる——-まさにこの作品に与えられるべき言葉であると思います。「砂漠の王編」と「記憶の僕編」が交互に続く設定(しかも、電話ボックス、というのがまた面白く)は、慣れるまでの導入である入口の狭さは否めませんが、引き込まれた後はどんどん続く奇想な展開に前のめりになる感覚でした。決して万人受けする設定や文体ではなく、両親殺しに関する説明がOFFになっていることのフラストレーションが消えない等、一般的な小説としての不完全さは残っているのですが、それとは異なるフィールドで、斬新なアート系の単館系映画としての画を喚起させる力がある作品です。不条理な設定で、ある意味観客にわざと距離感を与えて突き放したまま——例えば3枚の100円玉等のガジェット的なものによる突飛な展開を提示してまたもや走り出す、というシュールさ加減が(文章的なものというよりはあくまで話の転がり方という観点からですが)、一部の人間には強く響きます。
『カルナ』 長月 雨音
まず、変化球作品の中でも随分高尚で不思議な作品が残ったなと思いました。シニア層にも好感を持って迎え入れられる小説だと思います。「カルナ」という感情の擬人化の設定や、生物の遺伝子が文化の進化や淘汰を司るという「ミーム」等の作者自身の経歴から来ているであろう言葉群も興味深く読ませて頂きました。象徴的ゆえに、この「ラブストーリー」のテーマ部分は形而上的な印象があるのですが、「カルナ」の正体という具体性や大学生の日常生活についての丁寧な書き込みや主人公と源爺との触れ合い等とのバランスが良く、物語自体のリアリティを損なうことなく世界観を共有できました。しかし、文芳との失恋に対して自殺を考えた主人公が、やっぱり自殺に向かっていくという設定には(特に女性には)、感情的な面で共感を持ちにくいように思います。主人公の不甲斐なさについての疑問と苛立ちが拭えない読後感が、残念なことに純粋な感動を薄めてしまっているような気がします。
『夏の雪兎』 高田 在子
今回の最終選考作品の中で、一番の正統派系の作品だったと思います。恐らく、この文学賞に対して注目するコア層と思われる、20代・30代の女性読者たちからの共感(負け犬一歩手前の焦りの心情吐露や職場でのフラストレーション等)が、最終選考作品の中で最も得やすかった作品ではないでしょうか。主人公・千可子の過去の消えない傷、という入口も入りやく、雪兎が彼女を実は数年前から知っていた、というバラシも面白く読みました。ただし、中盤で主人公が会社を辞めてしまってからは、「働く女性の話」ではなくなり、純粋な「ラブストーリー」に転化します。そこからメインテーマになってくる、EDという問題が急に記号的で(一般の読み手にとっては)非日常的な世界に入ってしまうことに対しては若干置いてきぼり感がありました。また、評価が集まる「丁寧なキャラクターの書き込み」の部分は、映画では残念ながらストーリーの動きとはまた別のものなので、話の内容に立ち返って見た時に少々物足りなさが残ってしまいました。
『style』 広木 赤
1・2次審査を沸かせたという応募作の噂を聞き、興味深く手に取りました。これもまた面白い変化球です。延々と「静」の世界が続き、やっと終盤で主人公二人が会話を交わしたところで「何か起こるとしたら、さぁ、これから」という少し希望的な「揺らし」で終わる、という結末ゆえ(そのため、意外に読後感は爽やかですが)、「映画」としては話が殆ど動いていない——その一方で「映像」のイメージがやたら見える、という二律背反的な作品でした。作者は男性なのに、ヒロイン・猫子の日常の描写が非常にリアルかつポップで好感が持てた一方、男性主人公・一弥の淡々としたキャラクターに(作者自身に近い経歴にもかかわらず)逆にリアルさを感じず、薄い印象だったのが残念です。また、もう一点気になったのが、猫子の「リストカット癖」。登場人物のキャラ付け用の「リスカ」という行為そのものは、もはや記号化された感があるので、正直食傷気味です。一方の「万引き」描写が生き生きしているだけに、「リスカ」が持ち出されてしまったこと自体が勿体無く思いました。