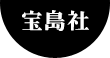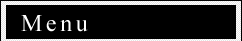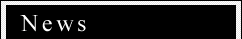最終審査講評
桜井 亜美 Sakurai Ami / 作家
『カフーを待ちわびて』 原田 マハ
沖縄の離島の空気感やゆったりとした時間の流れが、心憎いほど鮮やかに描写されている。キャラクター設定もうまく、文章も端正で心地よく読ませてくれ、完成度はかなり高い。沖縄好きな私には、リゾート開発に揺れる離島の人間関係はけっこうリアルに思えたが、逆にもう少し現実離れした世界に連れていってもらいたかったという読後感も残った。肝心の恋愛についていうと、幸が明青をなぜあれほど好きになったか、説得力が薄い。男のキャラはみんな、生き生きと体温を感じさせるのに、幸は抽象的で儚い亡霊のような印象だ。幸の葛藤や現実の明青と交わって変化していく心の過程などを描ききれれば、読後の感動もぐんとアップするはず。
『スイッチ』 佐藤 さくら
文句なしに面白く、ひきずりこまれた。読み始めたらとまらず、徹夜で一気に読んでしまったほどエネルギーがある。なによりもすべての登場人物が生き生きとしていて、生身の体温をリアルに感じさせる描写はすごい。主人公の他人とうまく溶け合えない自意識、それによって仕事も人付き合いもどんどんなし崩しになっていく生活ぶりは、多くの20代に「これって私(俺)じゃん」と強く共感させる説得力を持つ。ある意味、平成ニート世代版の「人間失格」なのかも。サル男との一見、クールに見える恋愛も、内面の切実さや「どうしても、彼でなきゃだめ」という実感がこもっていて、一番納得できるものだった。さらにこの作品を豊かにしているのは、脇役にも全員、豊かな血肉がかよっていて愛情をもって描かれているところ。中でも瑠夏や中島さんのキャラクター描写、主人公と結衣との関係の描写などは感動するほど秀逸。ただ、人との出会い方に偶然が多く都合がよすぎることが唯一の欠点なので、そこに工夫が必要だと思う。
『雨の日の、夕飯前』 中居 真麻
どことなく京都の古い旅館で、女将さんの若いころの恋物語を聞いているような雰囲気は、著者の職業のせい? 昭和初期の女流文学みたいな空気感は、なかなか心地いい。保護者の夫がいながら他の男と恋もしていて、という江國香織さん的な世界が好きな人ならどっぷりハマれそう。全体的に破綻はなく文章も巧いが、主人公の心理描写が平坦で緩急や収斂に欠けるので、私はいまひとつのめりこめなかった。それぞれの男との関係や別れに対する主人公の内面が、もっとヴィヴィッドに伝わってくるよう、工夫が必要なのでは? 上品さや抑制が、読者に傍観者的な距離をもたせてしまい、可もなく不可もなしという読後感になってしまった。
『恋をしないセミ、眠らないイルカ』 サトウ サナ
最初の「年老いたイルカの死に場所」という書き出しが、寓話的でとてもよかったので期待した。が、残念ながら期待だけに終わってしまった。主人公が殺人容疑で逮捕され、動機を話すために過去を回想するという設定自体は面白いが、それがうまく生きていないのは、肝心の犯行動機自体にまったく説得力がないため。あの程度の動機づけで出会ったばかりの妊婦を殺すとしたら、もっとその前段階に重い抑圧や葛藤がないとおかしい。それに現在のヘビーな状況から、甘酸っぱい回想に変わるときの、記憶の深層を分け入っていくような書き込みがないから、二つの世界を強引に張り合わせたような違和感が残る。文章やセンスはいいものを持っているので、もう少しキャラクターの行動の動機付けを練りこんでほしい。文体に村上春樹の影響を感じたのですが、どうでしょう?
『SONOKO』 片栗子
歴史をからめた壮大なスケールと、女性パイロットという設定の面白さは買い。飛行機大好きな作者の、飛ぶことへの情熱や愛情が熱く伝わってくる。でも、スケールを大きくするほど、その中に生きる登場人物の人間味や個性がくっきり浮かびあがらなければならない。この作品のキャラクターの会話はストーリーを展開するために、予め指示された言葉をしゃべっているようで、面白みに欠ける。さらにストーリー展開もプロットがしっかりしているのはいいが、逆に言えばそれがこの作品の限界ともいえ、最初から「ここで泣かそう」というラストのツボが見えてしまうのが、ちょっと残念。もっと矛盾やダークサイドを抱えたキャラクターがプロットに破れ目をいれるぐらいの、「乱調」や豊かさがほしい。
『埋め込み式。』 佐々木 やち
この作品で時々出会う、どきっとするほど鮮やかな文章力には、最高点をあげてもいいと思った。ただ、ディティールや登場人物の設定がひとりよがりで、わかり難く、それがせっかくの表現力を殺している。主人公が自殺した恋人への贖罪のために、自分に好意を持つ女たちを死に追いやるというダークな設定は魅力的だが、なぜ女たちがそんなに簡単に彼を愛してしまうかがまったく分からない。そのへんの書き込みがないから、ただのゲーム感覚で殺しているような薄さが眼についた。登場人物の会話も自意識の空回りになってしまっていて、読者には伝わってこない部分も多い。さらに主人公は地方新聞の記者という設定だが、記者がまるで作家的な職業であるかのようにとらえられている気がして違和感があった。この著者は自分の身近なよく知っている世界を舞台にしたときに、はじめてダークでアンニュイな作風や、切れのある文才が生きると思う。